荷役現場の“ギャップ”に目を向けてみましょう!
多くの荷役現場では、労働災害を防ぐために
「安全研修」「KY(危険予知)活動」「定例ミーティング」など、
時間をかけた取り組みが行われています。
しかし――
実際に事故が起こった後、当事者に話を聞いてみると
返ってくるのはこんな言葉です。
「えっ、聞いてなかったです」
「そんなルール、知らなかった」
「それって自分がやることだったんですか?」
しっかり説明したはずなのに、なぜこんなギャップが生まれるのでしょうか?
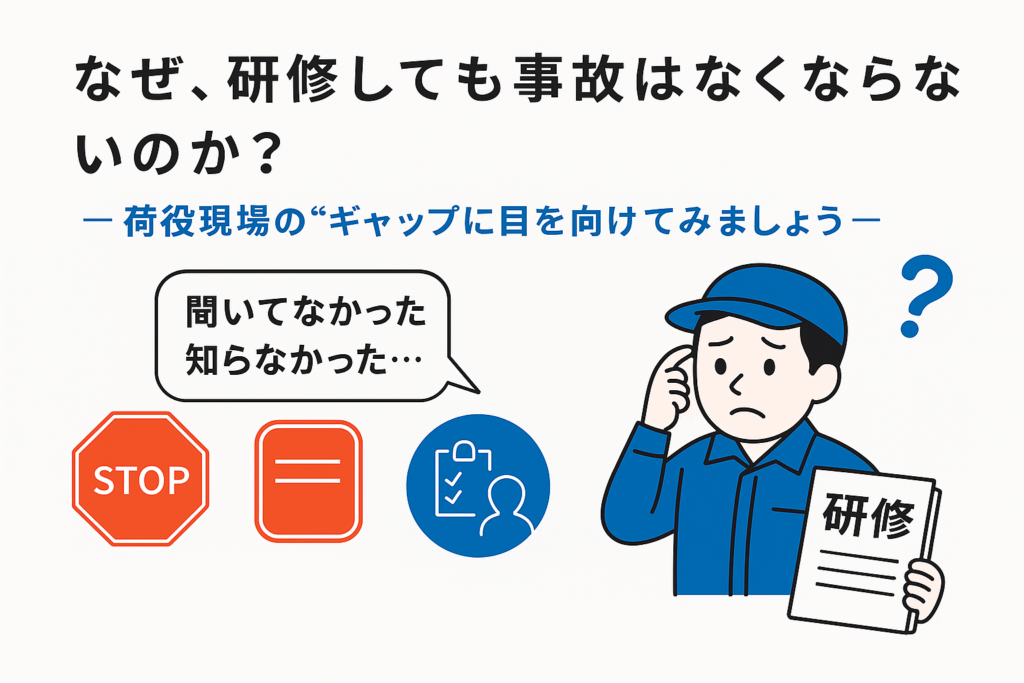
◆ 原因は「情報の伝わり方」にある
研修や指導では、「言葉」や「紙」で伝えるのが一般的です。
しかし、実際の現場では、次のような課題が起きています。
- 情報が頭に残らない(文字が多い、安全資料が分厚い)
- 現場でどの場面で使うのかイメージできない
- タイミング的に、教わってから作業するまでに間が空く
- 新人やパートさんは、わからなくても聞きにくい
つまり、研修やマニュアルで“伝えたつもり”でも、本人にとっては「行動に結びついていない」のです。
◆ 「知らなかった」をなくす一歩は、“見える化”から
このギャップを埋める方法のひとつが、*見ればわかる化サイン(DAPS)です。
たとえば――
- 「通行禁止エリア」に赤線+STOP表示
- 「荷物を置いてはいけない通路」に白枠をプリント
- 「荷役前の確認手順」を作業場所の壁に掲示
こうした視覚的なサインがあれば、
「現場で迷わず判断できる」「言われなくても気づける」という状態がつくれます。
これは、研修の補完だけでなく、日常の安全確認の“見えるガイドにもなります。
◆ 最後に
「ちゃんと研修してるのに、なぜ事故が起きるのか?」
その疑問の裏には、“伝える”と“伝わる”の違いがあります。
DAPS(デジアナプリントシステム)は、この“伝わる仕組み”を現場に合わせて創るためのツールです。
研修だけに頼らず、「働きながらルールが習慣化できる職場」へ。
その第一歩を、一緒に考えてみませんか?


