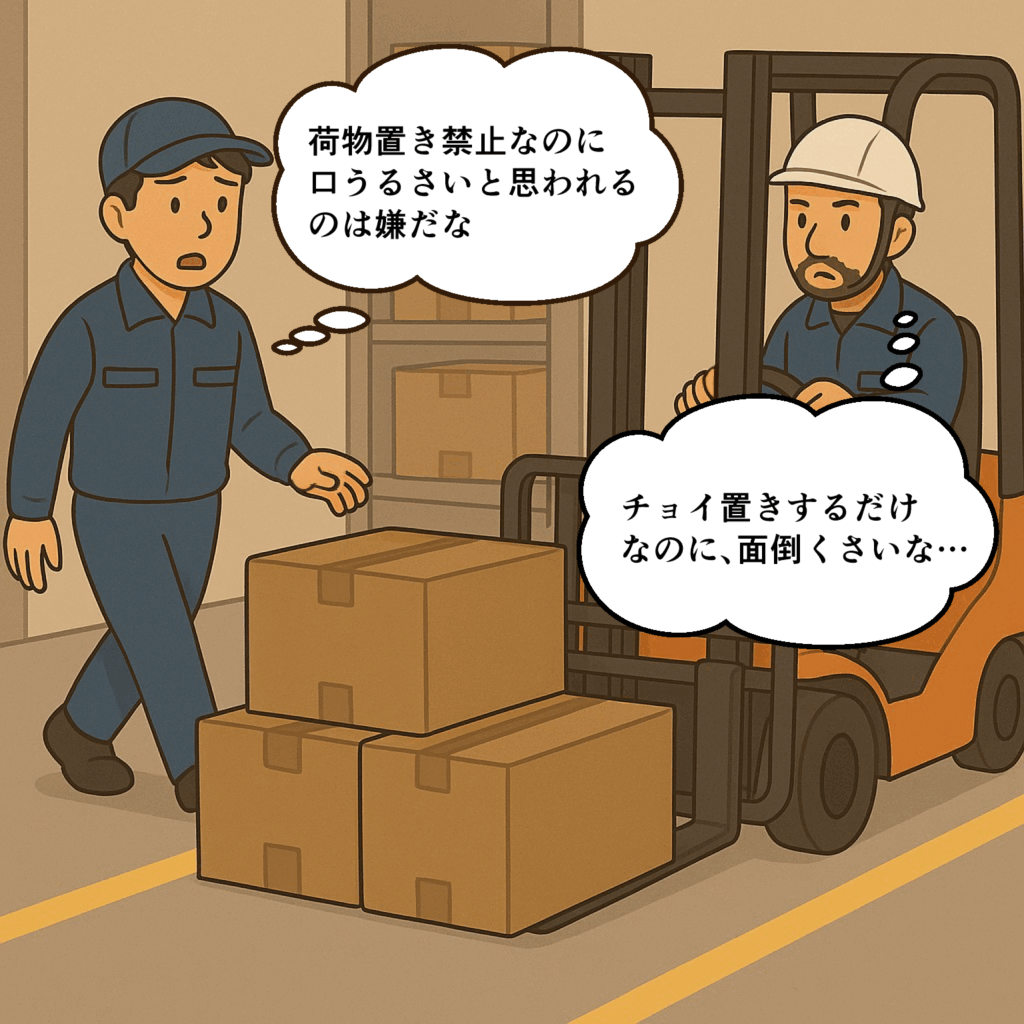現場でよく見かける光景――
フォークリフトのドライバーが、歩行帯に荷物を一時的に置き、歩行者が通れなくなってしまう。
そのたびにベテランや管理者が注意をし、歩行者は不満を抱きます。
しかし、リフトドライバーの心境はどうでしょうか。
(シチュエーション)
忙しい午後、リフトドライバーが急いで荷物を運んでいました。
「ここに少し置いて、すぐ次の荷物を取って戻れば大丈夫だろう」
そう思って歩行帯の上にパレットを下ろした瞬間、歩行者が来て立ち止まります。
それぞれの“心の声”
・リフトドライバー
「置く場所が無いんだ…。でも歩行帯に置いたらまた注意される。
正直、嫌われ役になるのはごめんだ」
・歩行者
「また荷物でふさがれてる…。遠回りしなきゃ。なんで毎回こうなんだろう」
・中堅スタッフ(注意する側)
「何度言っても繰り返される。自分ばかり口うるさい人に見えるのが嫌だ」
問題点
・荷物の一時置き場が明確でないため、ドライバーは“仕方なく”歩行帯に置く。
・その結果、歩行者は危険にさらされ、不満を募らせる。
・注意が繰り返されるが、構造が変わらないため解決につながらない。
「わかる化サイン」で変わる未来
もし、歩行帯に 「荷物置き禁止」 のサインが明示され、
その近くに 「一時置き場」 のサインが用意されていたら――
・リフトドライバー:「ここなら置ける」と安心して行動できる
・歩行者:「ここは安全に通れる」と信頼できる
・注意するスタッフ:「また言わなきゃ」のストレスから解放
結果として、
・歩行帯が本来の役割を果たす
・ドライバーも歩行者も気持ちよく動ける
・現場の空気が和らぐ
そんな環境が実現できます。
まとめ
リフトドライバーもまた、ルールを破りたくて破っているのではありません。
「仕方なく」「場所が無いから」といった事情の中で動いているのです。
注意ではなく、サインで“置いていい場所・ダメな場所”を明示すること。
それが、ドライバー・歩行者・管理者すべてを救う仕組みになるのです。