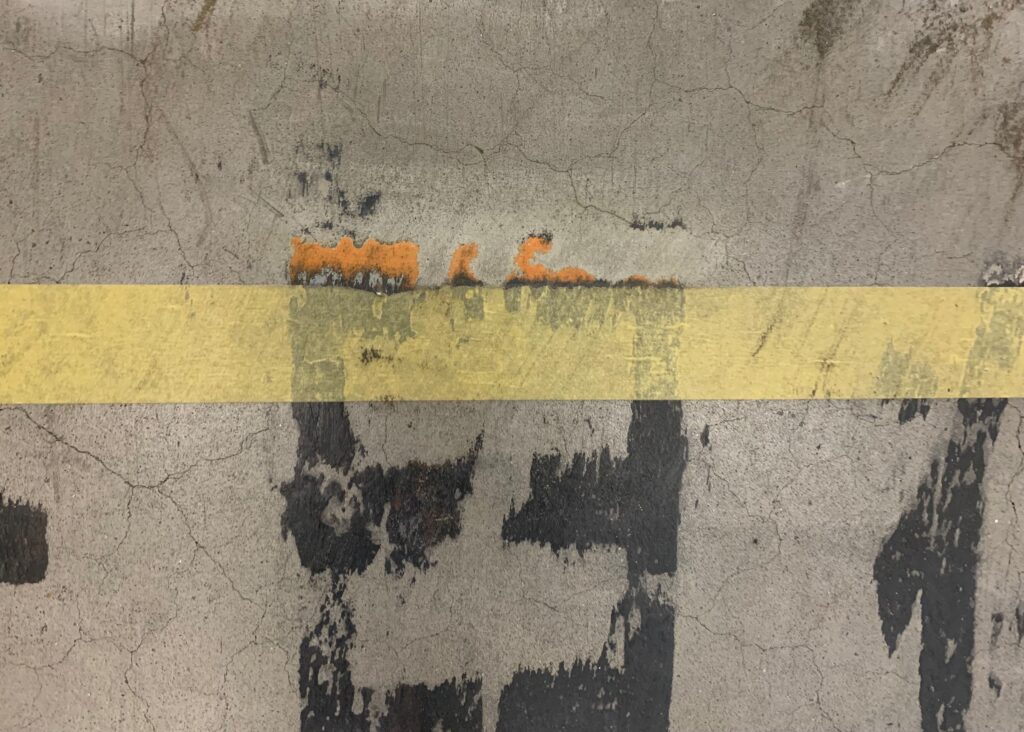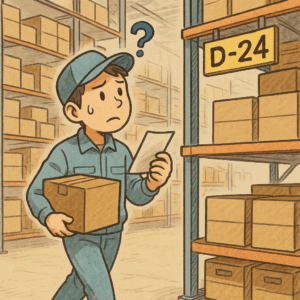■ 同じ会社なのに、安全対策が現場ごとにバラバラ?
物流企業では、拠点が増えれば増えるほど、現場ごとの安全対策に“ばらつき”が生まれます。
歩行帯の表示方法、リフトの停止位置のルール、荷役作業時の指差確認…
A倉庫では徹底されているのに、B倉庫ではまったく違う。
これは「管理がずさんだから」ではありません。
実は、現場ごとに異なる事情があるのです。
✅ 安全対策に差が出る5つの主な理由
① 荷物の種類が違うから
荷物の特性によって求められる安全対策は大きく異なります。
- 家電・精密機器 → 破損リスクを防ぐため慎重な作業と注意喚起が必要
- 飲料や日用品 → 回転効率が重視され、スピードと動線確保が求められる
そのため、表示内容も表示位置も変わって当然なのです。
② 自社倉庫と賃貸倉庫の違い
- 自社倉庫では、床への塗装やピットへのアンカー打ちなど、恒久的な施工が可能
- 一方、賃貸倉庫では、「現状復帰できない表示は禁止」というケースがほとんど
📌 貸主の制約でこんな声も…
「床に直接プリントできません」
「柱への取り付けはテープ止めのみで」
「退去時に完全撤去できるものだけにしてほしい」
このように、物件契約上のルールが、安全対策の自由度を制限しているのです。
③ 荷主の考え方が違う
荷主の安全意識が高ければ、サイン表示やルール整備に投資を惜しみません。
しかし、荷主によっては「安全より納期」「事故が起きてから考える」という考え方のケースもあります。
荷主が変われば、現場ルールも“がらり”と変わる
→ サインや注意喚起も現場ごとにバラつきます。
④ 委託倉庫と直営倉庫の違い
- 直営倉庫:自社社員が多く、教育やルール浸透がしやすい
- 委託倉庫(3PL):協力会社や派遣スタッフが多く、ルール徹底が難しい
人の入れ替わりが激しい現場では、「口頭指導だけでは不十分」なのが現実です。
⑤ 貸主の「原状復帰」要件による制約
先ほどの②と関連しますが、特に賃貸物件では、貸主による制限がサイン整備のハードルになります。
| 許可されない例 | 内容 |
| 床への塗装・インク印刷 | 原状回復が困難とみなされる |
| 壁へのビス留め・アンカー固定 | 穴が開くものは禁止 |
| 強粘着素材のシール | 剥がし跡が残る恐れでNG |
これにより、「せっかく安全対策をしたいのに、何もできない」という状況が発生してしまいます。
✅ 解決策:「見ればわかる」+「剥がせる」サイン
こうした制限があるからこそ、「わかる化サイン」+「再剥離型メディア」の組み合わせが有効です。
- 床や壁に貼れる「インクシール」なら、退去時にも剥がして原状復帰が可能
- 必要な場所に、必要なサイズで、安全ルールを“見える化”できる
つまり、現場ごとの事情に対応しながら、統一感のある表示が実現できるのです。
✅ まとめ:「違って当然」な現場に、共通の安全文化を
物流企業の現場は、荷物も契約形態も人も違います。
だからこそ、ルールが違って当たり前。
でも、そこで働く人にとっては「会社の安全対策」はひとつであってほしい。
わかる化サインなら、言葉・経験・文化を超えて「共通の理解」を届けることができます。