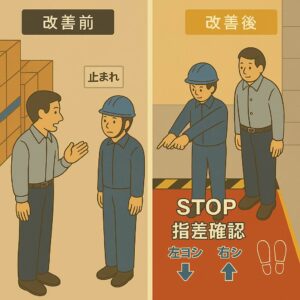■ 「やってください」と言い続ける限界
安全担当者や管理者の多くは、こう口にします。
「指差呼称を徹底してください」「決められたルールは守ってください」
――しかし、どれだけ呼びかけても、現場では徹底されない。
それが現実ではないでしょうか。
原因は、“人の意識”に頼りすぎていること。
毎日のように繰り返される指導や朝礼では、スタッフの緊張感は次第に薄れ、
「言われるからやる」だけの行動に変わってしまいます。
その結果、注意喚起は“作業の一部”に埋もれてしまうのです。
■ 意識を変えるのではなく、「行動が変わる」環境をつくる
人は、無意識のうちに「目に入る情報」で行動を決めています。
床に赤いSTOPサインがあれば、自然と足が止まり、
矢印があれば、左右を確認したくなる。
これは心理学的にも「視覚誘導効果」と呼ばれ、
人の判断を迷わせない“デザインの力”です。
つまり、安全を定着させるために必要なのは、
「意識改革」ではなく「環境設計」。
“守らせる”ではなく、“守れる”仕組みを現場に埋め込むことが、
真の安全文化への第一歩なのです。
■ 指差呼称が自然に生まれる職場とは
たとえば、交差点のSTOPサインのそばに「左右確認」の矢印があり、
その少し先に「安全第一」の文字が視界に入る。
そのようなサイン配置があれば、指差呼称は「意識してやるもの」ではなく、
自然に体が動く行動になります。
この“自然にできる”という状態こそが、
「見ればわかる化サイン」が目指す理想です。
サインがあることで、注意が促されるのではなく――
サインがあるからこそ、安全行動が習慣化する。
■ 現場の声を仕組みに変える
ルールを定着させるために最も大切なのは、
現場スタッフの意見を反映させることです。
「どの位置なら見やすいか」
「どんな言葉なら自然に行動できるか」
「どんな形や色なら目に残るか」
この“考えるプロセス”こそが、ルールを自分ごと化させる。
つまり、ルールの共有ではなく“共創”こそが安全文化の根幹なのです。
■ 安全は「伝える」ものではなく「伝わる」もの
言葉で何度伝えても、行動が変わらなければ意味がありません。
しかし、目に見える仕組みであれば、誰もが理解できます。
「見ればわかる」――その状態をつくることが、
結果として離職を減らし、安心して働ける職場を生み出します。
“指差呼称が自然に生まれる現場”とは、
人を責めず、仕組みで守る現場です。
これこそが、次の時代の安全対策のあり方ではないでしょうか。