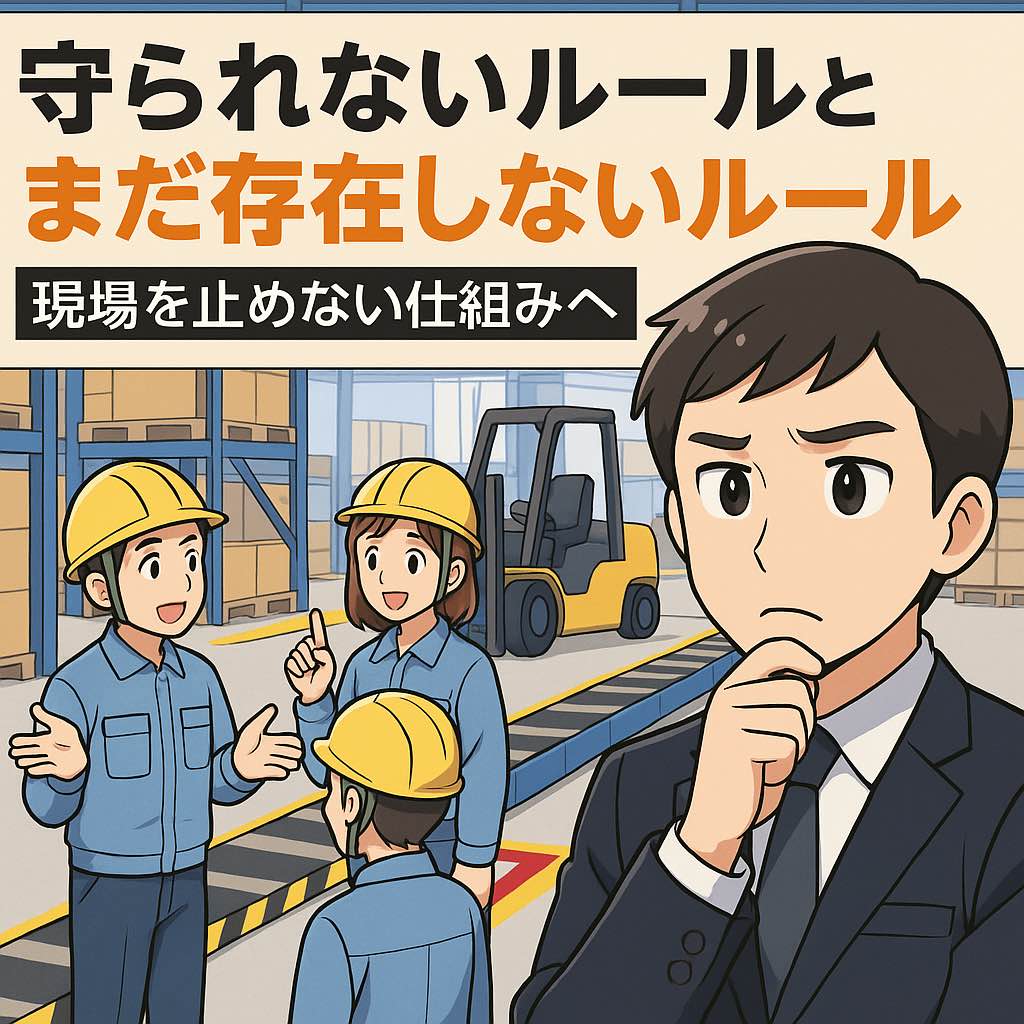■ 「想定していなかった」が通じない時代
事故が起きたとき、真っ先に問われるのは現場の安全管理者です。
「なぜこんなことが起きた?」
「想定できなかったのか?」
しかし、現場の管理者にとっては、
「そんな事故が起こるなんて、誰も考えていませんでした」というのが正直なところ。
それでも、上司は厳しい表情で言うのです。
「だからこそ、お前の仕事じゃないか」
新しい機械や設備が導入されても、事前の情報共有が十分でないまま運用が始まり、
結果として、事故が起きてから責任の所在を問われる。
そのたびに、現場と上層部の間には“気まずい空気”が生まれます。
■ 新しい設備に「ルールが追いついていない」
最近の現場で多いのは、機械と人の動線が交わることで生じる想定外の事故です。
たとえば、自動搬送ベルトコンベヤにリフトが接触して自動停止し、
メンテナンスが終わるまで物流が完全に止まってしまうケース。
これは、「ルールを守らなかった」事故ではありません。
ルールそのものがまだ存在していなかった事故です。
現場は日々変化しています。
新しい機械が入り、人の動きが変わり、レイアウトが更新される。
それでも、安全対策は“去年と同じチェックリスト”で運用されていることが多い。
これでは、管理者がどれだけ注意しても限界があります。
■ “わかる化”は、現場を巻き込む安全マネジメント
事故を防ぐには、管理者一人の努力ではなく、現場全員の目線が必要です。
わかる化サインの強みは、まさにそこにあります。
ルールや危険箇所を“見える形”にすることで、
スタッフ自身が「ここにも必要では?」と考えるようになる。
「こんな自由なデザインで床に表示できるなら、あそこにも使ってみましょう」
「この新しい設備の周囲にも、表示を足した方が良いかもしれません」
そうした声が自然に出てくる現場では、
管理者が一人で“想定”するのではなく、
全員で“想定外を減らす”体制が生まれます。
これが、上司に対して説明できる本当の安全管理。
「現場任せではなく、現場を巻き込んだ安全活動をしています」と言える仕組みなのです。
■ 責められる管理から、信頼される管理へ
わかる化を導入することで、
安全管理者は「起きたことの説明役」から「起きないように設計する役」へ変わります。
現場の声を拾い、サインで可視化し、
全員が同じ基準で動ける環境を整える。
これによって、上司も「よく考えている」と感じ、
管理者への信頼が積み上がります。
つまり、わかる化サインは“安全のための道具”であると同時に、
「管理者の立場を守る仕組み」でもあるのです。
■ まとめ
・守られないルールは、環境が整っていないサイン。
・存在しないルールは、変化に追いつけていないサイン。
・そして、“想定外をなくす仕組み”が、わかる化サイン。
現場を見て、感じて、考えた意見がサインとして形になれば、
安全管理は「責められる仕事」から「信頼される役割」へ変わります。
“守るためのサイン”から、“考えを共有するサイン”へ。
それが、次の時代の安全管理の姿です。