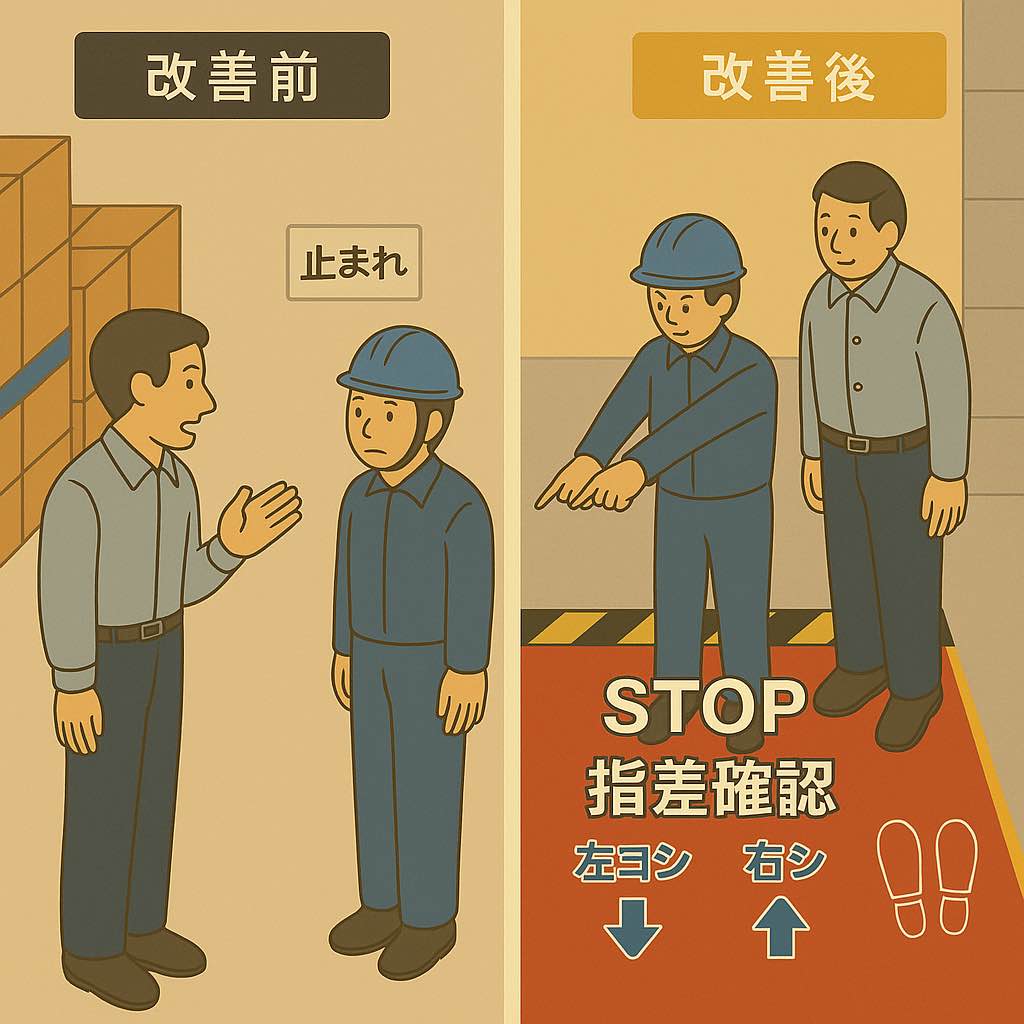■ 「何度教えても、また同じミスが起きる」
安全管理担当者の多くが抱える共通の悩みです。
新人研修をしても、数日後には忘れてしまう。
ベテランからは「何度言ったらわかるんだ」と不満が出る。
結果として、同じトラブルやヒヤリハットが繰り返されてしまう。
こうした現象の背景には、
「教育の属人化」と「仕組みとしての継続性の欠如」という
構造的な問題があります。
■ 1. 教える人が変わるたびに、やり方が変わる
倉庫では人の入れ替わりが多く、
そのたびに教育担当が変わり、指導内容もバラバラ。
「昨日と今日で言っていることが違う」――そんな現場も少なくありません。
この状態では、ルールは“共有”ではなく“個人の感覚”で運用されてしまいます。
結果として、「言っても伝わらない」現場が生まれます。
■ 2. 忙しさの中で、「見て覚える」が常態化
「見ればわかる」「やってみれば覚える」――。
そんな言葉が、教育の代わりになっていませんか?
この“見て覚える”スタイルは、一見効率的に見えて、
実は現場の再現性を奪う最大の要因です。
教える人によって伝わる内容が違い、
誤った手順が“現場の標準”として定着してしまう危険があります。
■ 3. 形式的な教育では、行動は変わらない
多くの倉庫では、入社時研修や年1回の安全教育が行われています。
しかし、それ以外のタイミングで“確認の仕組み”がないため、
時間が経つと意識が薄れ、ヒヤリ・ハットが増えていきます。
教育は「イベント」ではなく「習慣」でなければ、効果が続きません。
■ 4. 現場で“教えやすく、覚えやすい”環境づくりがカギ
教育の質を変えるのは、“伝え方”ではなく仕組みです。
たとえば、
・危険箇所に「STOP」「指差確認」などのわかる化サインを表示する
・作業手順やルールを床・壁のデザインで共通化する
・言葉ではなく、見れば理解できる状態をつくる
こうした工夫によって、
誰が教えても同じ内容が伝わり、
言葉や経験の差を超えて“正しい行動”を定着させることができます。
■ 5. 教えるより「伝わる」仕組みを
ルールを守らせるための教育ではなく、
ルールが自然に身につく環境をつくること。
これが、現代の安全管理者に求められる役割です。
“見える化”から一歩進んだ、「わかる化」こそ、
教育の形骸化を防ぎ、行動を変える第一歩です。